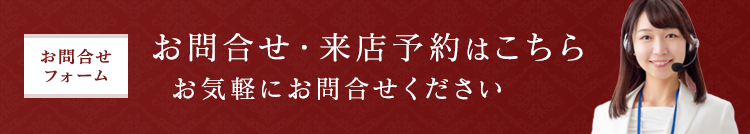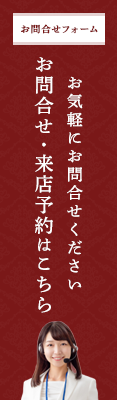ペルシャ絨毯にダニは付くのか?

[画像:ツメダニ]
絨毯は湿気や食べカス、皮脂などが付着することで、ダニの温床となることがあります。
とくに長期間掃除せずに放置すると、ダニの繁殖が進むことも。
絨毯はダニの隠れ家として適した環境となりやすいため、定期的な掃除や手入れが必要となります。
ダニが付くのは機械織絨毯だけでペルシャ絨毯には付かないと説明しているサイトがありますが、そんなことはありません。
ペルシャ絨毯は機械織絨毯と違い結び目があるので、ダニが奥まで入りづらい、またICCのように防虫効果のある藍で染めた横糸を使用しているものはダニが寄り付きにくいといったことはあるかもしれません。
しかし、環境によってはダニが住み着く可能性がないとは言いきれないのです。
要はダニが住みつきやすい環境を作らないこと。
つまり、日々の「手入れ」こそが不可欠なのです。
ダニによる虫刺されの原因としては、ネズミに寄生するイエダニによる被害が多いようです。
イエダニは体長0.6~1.0mmほどで、寝ている間に寝室内に侵入し、衣類の中に潜り込んで吸血します。
6月から9月頃に発生し、感染症を媒介することもあります。
古い一戸建てで、床下や天井裏などにネズミが生息するような家で被害が発生しやすいです。
脇腹や下腹部、太腿の内側などの柔らかい刺して、かゆみの強い赤い発疹ができます。
最も恐ろしいダニですが、ネズミさえいなければ被害に遭う可能性はあまりないでしょう。
実は家にいるダニの7~9割を占めるのがヒョウヒダニ(チリダニ)類です。
その中でも比率の高いヤケヒョウヒダニは0.2~0.4mm程度のサイズです。
肉眼では判別が難しいですが、ほぼ1年中いるダニで、布団、カーペット、布製のソファなどをはじめ、人間が生活しているほとんどの場所に生息していると言われています。
ヒョウヒダニ類は死骸や糞がアレルゲンになってしまうためアレルギー症状を引き起こすことがありますが、人を刺すことはありません。
問題なのは、このヒョウヒダニや食品につくコナダニを捕まえてその体液を吸って生息しているツメダニです。 これは人を刺すダニです。
ツメダニは体長0.3~1.0mmほどで、絨毯や畳、ソファーなどに潜んでいて、他のダニや小さな昆虫などをエサにしています。
エサになる虫が増える梅雨時~秋にかけて繁殖が盛んになるので、8~9月は特に被害が多い季節です。
ツメダニ刺されると赤く腫れて痒みが1週間ほど続きます。
高温・多湿を好むダニは5~9月に特に繁殖しますが、近年は暖房が普及しているため冬でも生息しています。
気温20~30℃で湿度60~80%の、人間にとって過ごしやすい環境は、ダニにとっても居心地がよいのです。
ダニを予防するためにはペルシャ絨毯を定期的に掃除機で吸引し、埃や食べカスなどを取り除くことが大切です。
また、ペルシャ絨毯を定期的に日陰干して換気することで、湿気を逃がし、ダニの繁殖を抑えることができます。
どの家にもダニは必ずいます。
そして、残念ながらゼロにすることは不可能です。
ダニは、人間のフケやアカ、埃、その他有機物を食べて増殖します。
繁殖しやすい条件が揃うと、1組のつがいが2ヵ月後には約3000匹、さらに4ヵ月後には約450万匹…というように爆発的に増殖してしまうのです。
また、フケやアカなどのエサがたった1gあれば、約300匹が生息できてしまいます。
換気をして湿度を下げ、熱と乾燥に弱いダニが住みにくい環境にしておくことが大切です。
また入念に掃除をしてダニのエサを減らし、ダニの繁殖しにくい環境を作りましょう。
具体的には以下の対策が必要となります。
1.定期的な掃除
絨毯を掃除機で定期的に掃除し、ホコリやダニの卵を取り除くことが重要です。
専用の絨毯ヘッドを使用すると効果的です。
2. 専門のクリーニング
年に一度、または必要に応じて専門のクリーニングサービスを利用することで、深部に入り込んだ汚れやダニをほぼ完全に取り除くことができます。
3. 湿度管理
部屋の湿度を適切に保つために、除湿器やエアコンを使用し、湿気を抑えることが大切です。
4. カバーの使用
収納時にはダニ対策用のカバーを使用することで、ダニの侵入を防ぐことができます。
これらの対策を講じることで、ペルシャ絨毯を清潔に保ち、ダニを減少させることができます。