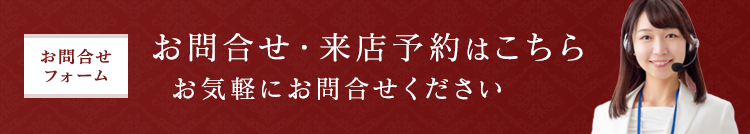はじめに
1931年(昭和6年)に撮影された旧渋沢邸第2応接室の写真からは、3枚のペルシャ絨毯の存在が確認できる(図1参照)。
そのうち長椅子の下に敷かれた絨毯については、特徴的なデザインからイラン中央部のジョーシャガン、あるいは隣接するメイメで産したものと容易に識別できた。
しかし、他の2枚については産地の特定は難航したのが正直なところである。
とりわけ、室内中央に敷かれた大きな絨毯は第2応接室の再現における核ともなるため、十分に納得のゆくものとなるよう時間をかけて考察と調達にあたった。
産地の究明
1枚のモノクローム写真だけで90年以上前に製作された絨毯の産地を特定するのは、多くの場合、困難が伴う。
イランにおける絨毯産業の復興期である19世紀後半から20世紀初頭にかけては、いくつかの産地において、よく似たデザインの絨毯が製作されたからである。
悠久の歴史を持つといわれるペルシャ絨毯であるが、その産業が1世紀以上に渡って途絶えていたことを知る人は、あまりいない。
絨毯産業を支えていたのは時の宮廷であったから、1722年のアフガン人の侵攻によりサファヴィー朝が滅亡すると、パトロンを失った絨毯工房は軒並み廃業の憂き目を見た。
以来19世紀後半に至るまで、この産業が復興することはなかった。
復興を主導したのはイラン北西部の商業都市であるタブリーズの商人と、ジーグラー商会やOCMなどの外国企業であった。
産業革命以降の中産階級の拡大とともに、欧米における高級絨毯の需要は高まっていた。
彼らは、そこに目をつけたのである。
当時のイランは度重なる戦争と内乱とにより政治は腐敗し、経済は疲弊していた。
町には失業者が溢れていたから、絨毯工房が開設されると、生活に困窮していた市民たちは絨毯織りの仕事に飛びついた。
産業はたちまちにして全土に広がり、見事に復興を遂げる。
絨毯産業の復興により、ペルシャ絨毯を製作する町や村はイラン全土に広がった。
いまや主な産地だけで100を優に上回り、名もないような小さな村をも数えると数百に上るとさえいわれる。
イラン全土で製作される絨毯の数は天文学的となるが、熟練の絨毯商であれば絨毯を見ただけで産地を特定することができる。
デザインは、もちろん判断材料の一つとなる。
しかし、先に述べたようにデザインのバリエーションが少なかった復興期においては、複数の産地において、よく似たデザインの絨毯が製作されている。
また、産地による程度の差こそあれ、デザインは時代とともに変化するから、新しい絨毯のデザインを元にして産地を特定するのにも限界がある。
産地を特定する決め手となるのは、絨毯の構造(縦糸の重なり方や横糸の数)、パイルの結び方(ペルシャ結びかトルコ結びか)、染料の種類(たとえば、赤ならアカネかコチニールか)などであるが、第2応接室の写真からは、そのいずれもが判別できない。
あらゆる可能性を取捨選択し、さらにオリエントの絨毯について研究が進んでいる欧米の識者の意見を参考にして考察を重ねた結果、第2応接室の絨毯の産地についてはイラン中東部のドロクシ、あるいは中西部のマラヤー(ペルシャ語の発音ではマライエル)で製作されたものである可能性が浮上した。
ヘラティ文様
第2応接室の絨毯には、菱形のトランジの中にヘラティらしき文様が認められる。
ヘラティ文様は花の正面形であるロゼットを囲った菱形の四方を、花の側面形であるパルメットとアカンサスの葉で飾ったものである。
アカンサスの葉の形状が魚に似ていることから、イランではペルシャ語で魚を意味する「マヒ」とよばれる(図2参照)。
アカンサスは地中海沿岸を原産とする多年草で、わが国ではハアザミとして知られている。
アカンサスの葉は古代ギリシャの時代から、建築装飾や室内装飾のモチーフとされてきた。
現存する17世紀のペルシャ絨毯にも、このモチーフが用いられているが、オーストリアの美術史家であったアロイス・リーグルによれば、エジプトで発祥した原始的なパルメットがギリシャに伝わり、写実的なアカンサスの葉に姿を変えたのち、イスラム圏において図形化されたという。
ノルウェー在住の識者は、おそらくバクチアリ産だという。
バクチアリはイラン中央部のチャハルマハル・バクチアリ州を中心に、イスファハン、ルリスタン、ブーシェフルの各州に居住するペルシャ系部族である。
たしかに、古いバクチアリの絨毯には似たようなデザインのものがある(図3参照)。
筆者にしても、その可能性を考えなかった訳ではないが、バクチアリの絨毯にヘラティ文様が用いられることはないので、バクチアリ産説は除外することにした。
2つの産地
産地の候補となったのは、ホラサン、アゼルバイジャン、クルディスタン、ハマダン、アラク、ヤズド、ファースの各地方であるが、第2応接室の絨毯は外側のボーダーにフランス風の花文様らしきものが認められる。
19世紀後半から20世紀初頭にかけては、フランスのオービュッソンやサボンネリエのデザインを採用した絨毯が、イランの各地で製作された。
しかし、その花文様には産地ごとによる特徴があって、第2応接室の絨毯の花文様は繊細で上品な印象である。
候補のうち、これをもとに篩にかければホラサン地方とハマダン地方が残る。1920年代までにフランス風の花文様の絨毯を製作していた産地は、ホラサン地方ならドロクシ、ハマダン地方ならマラヤーである(図4参照)。
マラヤー産として取引される絨毯については、西のウシュバンやネハーバンド、東のジョーザンやタイメ、南のボルジェルドなどで製作されたものを含めることがある。
しかし、それらの町や村で製作される絨毯はデザインが、ジョーザンやタイメに至っては構造もが明らかに異なっている。
これらを一括りにするには無理があるから、ここではマラヤー以外で産した絨毯は別にする。
本題に戻ろう。
第2応接室の絨毯は細めのボーダーが二列になっている。
ボーダーとは絨毯の枠にあたる部分のことで、主部となるフィールドを飾る額縁の役目を果たすものである。
ボーダーは太いメイン・ボーダーの両側を細いガード(サブ・ボーダーとも)で囲むのが一般的であり、ほとんどのペルシャ絨毯のボーダーがこのスタイルになっている。
よって、第2応接室の絨毯のものは、きわめて特異であるといってよい。
この特異なボーダーを持つのも、ドロクシ周辺やマラヤー周辺で製作された一部の絨毯に限られる(図5参照)。
となれば、選択肢はこの2つの産地に絞られる。
実は、この二つの産地で製作された絨毯を見分けるのは難しいことではない。
ドロクシではペルシャ結びが用いられるが、マラヤーではトルコ結びが用いられる(図6参照)。
また、ドロクシの絨毯は2本の横糸を交互に掛けるダブル・ウェフトの構造であるのに対し、マラヤーの絨毯は横糸を1本だけ用いるシングル・ウェフトの構造である。
したがって、この2点に着目すればよい。
ただし、これは絨毯の裏面を見ることができる場合に限った話である。
裏面の写真さえあればと悔しさに苛まれるが、ないものねだりをしても仕方がないので更に究明を試みる。
ドロクシ産との確信に至る
第2応接室の絨毯は、おそらく9平米以上の大きなサイズである。
ドロクシでは大きなサイズの絨毯が数多く製作されていたが、マラヤーで製作されたのは3平米以下の小さなサイズのものが中心であった。
マラヤーで大きなサイズの絨毯が製作されなかった訳ではない。
しかし、それは顧客から注文を受けた場合に限られており、大きなサイズのマラヤー産絨毯を見かけることは稀である。
また、絨毯の形状に目をやれば、第2応接室の絨毯は縦横の比が3対2から4対3ほどはあるように見受けられる。
マラヤー産の大きなサイズは2対1ほどのやや細長い形状のものが多いが、ドロクシ産はそれよりも幅が広いものが多い。
ここまでの考察の結果、ドロクシ産である可能性が高くなったが、それを確信するに足るものが見つかった。
“HOME BLOG by ROOMS TO GO” というサイトに掲載されている、1枚の絨毯がそれである(図7参照)。
このサイトのペルシャ絨毯についての情報は正確であり、資料的価値が高い。
1900年頃にホラサン地方で製作された、この絨毯は第2応接室の絨毯に酷似している。
細部のデザインは異なるものの、基本的なデザインの構成は同じである。
他の産地の絨毯にも似ているものはあるが、これほどではない。
ちなみに、紹介したサイトの絨毯はホラサン産となっているが、ホラサン地方は広大であるがゆえ、いくつもの絨毯産地が存在する。
現存する古い絨毯の中にはホラサン地方で製作されたことは定かとはいえ、町や村を特定できないものがある。
その場合、産地をホラサンとするのが慣例である。
これはファース地方の絨毯についても同じで、ファース地方最大の町であるシラーズのバザールに集積された絨毯のうち、製作した村や部族が特定できない絨毯はシラーズ産として扱われる。
この絨毯はホラサン地方の中でも、かつてクヘスタンとよばれた地域で製作されたものである。
クヘスタンはペルシャ語で「山の国」を意味し、アフガニスタンとの国境に近い山岳地帯にある(図8参照)。
ドロクシのほか、ビルジャンド、ムード、ガインなどの絨毯産地を擁し、ホラサン地方における絨毯産業の一大拠点となっている。
第2応接室の絨毯がクヘスタンで製作されたものならば、フランス風の花文様から産地はドロクシと特定してよいであろう。
装飾家の絨毯
ドロクシは現在の南ホラサン州ビルジャンド郡にある、人口2,000人ほどの村である。
州都ビルジャンドの北東、約50キロに位置している。
19世紀後半に始まるイランにおける絨毯産業の復興期、この村でも絨毯製作が本格化した。
20世紀中頃までにドロクシで製作された絨毯には多様なデザインが認められるが、ヘラティ文様と、インドのムガール絨毯の影響を受けたペイズリー文様が代表的といえる(図9参照)。
フィールド一面を複雑な文様で埋め尽くす様から「装飾家の絨毯」とよばれ好評を博した。
19世紀末にはフランスの敷物に倣った明るい色調のものも製作されたが、20世紀に入ってからのものは、やや暗い色調のものが多い。
それはドロクシに限らず、ホラサン地方で製作された絨毯の特徴で、赤色には一般にコチニールが用いられる。
コチニールは中南米原産のカイガラムシの一種で(図10参照)、ウチワサボテンに寄生するこの昆虫の雌を乾燥させたのち、擦り潰して染料にする。黄みを帯びたアカネとは異なり、染めあがりは青みを帯びた赤色になる。
なお、現在ドロクシ周辺で生産されている絨毯は、市場においてビルジャンド産あるいはムード産として売買されている、同一デザインの大量生産的なものである。
ドロクシが絨毯産地としてのアイデンティティを発揮し、数々の名品を世に送り出していたのは、第2次世界大戦の頃までといえよう。
この村で製作された絨毯は主にフランスに向けて輸出されていたため、ドイツの侵攻によりフランス本土が戦場となってからは輸出量が激減し、絨毯産業は凋落してしまった。
ドロクシ産絨毯が装飾家の絨毯として称えられたのは、いまは昔の話となっている。
調達にあたって
考察に基づき、20世紀初頭に製作されたドロクシ産絨毯を調達したいと考えていたところ、幸いにして希望する条件に近いものがドイツで見つかった(図11参照)。
第2応接室の絨毯がドロクシで製作されたものであるとすれば、この絨毯が産地を一にするものである根拠について述べてみたい。
製作年代については縦横糸にウールではなく木綿が使用されており、デザインも垢抜けていることから、ドロクシにおける絨毯産業の最盛期であった1910年代から1920年代にかけて製作されたものと推定した。
アンティーク絨毯の市場において、ドロクシ産絨毯の人気は高い。
同じ時期に大量に製作されたケルマン産やカシャーン産などの入手が比較的容易であるのに対し、もともと生産数が限られていたドロクシ産絨毯は現存する数が圧倒的に少ないからである。
ホラサン地方の絨毯特有のやや暗い色調も、ことにヨーロッパにおいては好まれる。
調達についてはヨーロッパ、中でもペルシャ絨毯の3大貿易センターの一つとして知られるドイツを中心に試みた。
ここでペルシャ絨毯の原産国たるイランを除外したことに疑問を抱くかもしれない。
実は、かつて浮世絵の名品を海外に流出させた我国と同じ事情がイランにはある。
イランではアンティーク絨毯は入手が困難であり、きわめて高価なのが現実である。
さらに、製作されてから100年を経過した絨毯については、文化財保護の理由から輸出が禁じられている。
条件に合うものがなかなか見つからず調達は難航したが、ふとした偶然から一枚の絨毯が目に留まった。
サイズは希望していたものより大きかったものの、ほかの条件は見事に一致している。のちにサイズについても丁度よいことが判明するのであるが、全体的にヘラティの変形らしき文様やパルメットが配されている点も第2応接室の絨毯に共通する。
ヘラティ文様については先に述べたが、パルメットについても少し解説しておく。
パルメットは花の側面形であるが、花についてはユリであると説明されることがある。
しかし、それは間違いで、正しくはハスの花である。
ハスは水に浮くことから、イランやインドでは豊穣のシンボルとされてきた。
ペルシャ絨毯に用いられる文様としては、もっともポピュラーなものであり、デザインのバリエーションも実に多い(図13参照)。
イランでは「シャー・アッバシー」とよばれるが、これはサファヴィー朝第5代君主であったアッバス1世(在位:1588〜1629年)の名に由来したものである。
ただし、アッバス1世と、この文様との間に直接の関係はないというのが真相のようである。
ペルシャ絨毯には、同じデザインのものが2枚と存在しないとの話を聞いたことがあるかもしれない。
ところが、これは絨毯商がよく用いるセールストークで、実際には意匠図は何度も使い回しされる。
つまり、同じデザインの絨毯は何枚も存在するということである。
しかし、現存数の少ないアンティークとなれば、ペアで製作されたものを除くと同じデザインの絨毯を見つけるのは不可能に近い。
仕入は一時のチャンスを逃してはならないのである。
これぞ唯一無二の品と確信した筆者は、直ちに輸入の手続きに入ることにした。
ペルシャ絨毯としての総合評価
絨毯は2022年10月11日にライプチヒを発ち、翌日、成田に到着した。
通関を終え倉庫に届いた大きな包みを解き、隅々まで検品する。
織りの密度については1平方メートル中に約25万個と、イスファハンやカシャーンなどで製作された絨毯に及ばないが、デザインの完成度はきわめて高く、オールオーバーの作品としては目を見張るものがある。
この絨毯の評価すべき点は、デザインの素晴らしさもさることながら、保存状態のよさであるといえよう。
使用痕がほとんどなく、傷みやすいフリンジ(房)やエッジ(耳)もオリジナルである。
褪色も認められない。
アンティークであることを考えれば、これほどまでに優れた状態であることは奇跡的ですらある。
今日、インターネットオークションなどで、アンティークとして販売されているペルシャ絨毯を見かける機会は多い。
しかし、それらの中に本物のアンティークは僅かしか存在しないのが現実である。
アンティークはフランス語で古美術品を指す語として使われてきた。
しかし、その定義については明確ではなかった。
1934年に米国が通商関税法に「製造された時点から100年以上を経過した手工芸品、工芸品、美術品」と定めてからは、それが世界標準となっている。
世界貿易機関(WHO)でも、この定義が採用されており、アンティークであることが証明された場合、加盟国間における関税は免除されるのが通常である。
ちなみに、絨毯については100年に満たないものをセミアンティーク(ベリーオールドとも)、オールドとよんで区別しているが、製作されてからの年数については国によって定義に若干の相違がある。
アンティークの価値が、その希少性にあるのは間違いない。
しかし、アンティークならば高価だと考えるのは早計である。
とりわけ、絨毯については18世紀以前に製作された学術的に貴重なものは別にして、保存状態がその価格を大きく左右するのが現実である。
全体的にパイルが擦り切れていたり、致命的な修理痕跡があるものなどは、アンティークとはいえ新しい絨毯よりも安価で取引されることも多い。
手工芸品、工芸品、美術品であれば、鑑賞に耐えられるものであるか否かが鍵となるのは当然であろう。
渋沢家とペルシャ絨毯
調達を終えて安堵したところで、改めて第2応接室の写真に目をやった。
旧渋沢邸の洋館が建築されたのは1929年(昭和4年)のことである。
当時、栄一翁は飛鳥山に本拠を移していたので、洋館を増築したこの屋敷のオーナーであったのは、孫の敬三氏に違いない。
ペルシャ絨毯についての記録がほとんど残っていないことから、昭和の中頃まではペルシャ絨毯をインテリアに取り入れる家庭は、きわめて稀であったと考えられる。
ならば、これらのペルシャ絨毯が如何なる経緯を辿って敬三氏の元にもたらされたのか。
絨毯商としては大いに気になるところである。
洋館の完成に伴い調度品を揃えたのは間違いなかろうが、1930年(昭和5年)に建築学会(現・日本建築学会)が発行した『窓掛と敷物』と題するパンフレットには、こうある。
「『ペルシャ』の『カーペット』は、手織『カーペット』の中、特に優秀なる製品にして、美術的價値も充分に具備して居る(中略)從つて價格も高貴なる爲め實用に供するより、 室内裝飾用として壁掛に用ひられ、貴重なる絨氈として取扱つて居る」。
筆者の宮内順治氏は高島屋呉服店(現・高島屋)の家具装飾部主任であった。
また、1935年(昭和10年)に三越が開催した「波斯段通陳列會」のカタログを目にする機会があったが、大きなサイズの絨毯は掲載されていなかったと記憶する。これらから推察するに、当時、わが国には大きなサイズのペルシャ絨毯が輸入されていなかったのではなかろうか。
もし、そうであるなら入手先はどこであったのか。
敬三氏は1921年(大正10年)に東京帝国大学経済学部を卒業し、横浜正金銀行に入行。
翌年には岩崎弥太郎の孫である木内登喜子と結婚したのち、ロンドン支店勤務を命じられ、英国に渡っている。
ロンドンは20世紀中頃までにおける、ペルシャ絨毯取引のヨーロッパ最大の拠点であった。
当然、町でペルシャ絨毯を目にする機会は少なくなかったろう。
同じ頃、ロンドンに留学していた清水組(現・清水建設)の森谷延雄氏が『木工と裝飾』に寄せた「絨毯の話」と題する記事には「ペルシャ絨毯の大半はこれ(筆者注:トルコ絨毯)に反して特殊の大形のものが主に成っているので、歐洲の室内にはその國で製作せられた敷物のごとく適合せられる理に行かぬ場合がある」とある。
敬三氏は廃嫡となった父親の篤二氏に代わり、すでに渋沢家の後継者となっていた。
入行2年目の銀行員とはいえ渋沢同族株式会社の社長でもあったから、ロンドンでそれらを購入した可能性は十分にある。
敬三氏は栄一翁の体調が芳しくないため、1926年(昭和元年)に帰国し、横浜正金銀行を退職。第一銀行の取締役ならびに澁澤倉庫の取締役に就任している。
敬三氏がペルシャ絨毯を求めた頃は経済人として盛んに活動し、自邸の応接室にも政界・財界の歴々が訪れていたことは想像に難くない。
一方で、仕事の傍ら民俗学に傾倒し、市井の民俗学研究者を多数、経済的に援助していたとも伝えられる。
豪華な調度品を買い揃えることは経済的に難しかったかもしれない。
となれば、着目すべきは祖父である栄一翁の存在である。
愛する孫で後継者でもある敬三氏が洋館を増築した祝いとして、これらの絨毯を贈った可能性は捨てきれない。
洋館が完成する少し前の1924年(大正13年)に、栄一翁は日仏交流の拠点として日仏会館を設立し、理事長に就任している。
当然、会館や大使館の関係者から入手した可能性もあり得るであろう。
ドロクシ産絨毯が主にフランスに向けて輸出されていたことに鑑みれば、むしろ、こう考える方が自然かもしれない。
真相は闇の中であるが、いずれにせよ、流麗なデザインで豪華な印象のカシャーン産やケルマン産ではなく、やや土臭さが感じられるドロクシ産やジョーシャガン・メイメ産を選んだところに渋沢家の人たちの個性が表れていて面白い。
これらの絨毯は趣味人が好むもので、いわば玄人向きである。
縁もゆかりもない渋沢家の人たちが急に身近な存在に感じられた。
おわりに
2022年8月に旧渋沢邸第二応接室のペルシャ絨毯の考証・調達の依頼を受けてから2ヶ月余にわたり、資料を漁る日々が続いた。
産地については、いくつかの候補が見つかったものの、いずれも決定打を欠いており、確信を持てずにいたのである。
そこで、筆者が参加するインターネット上の2つのアンティーク絨毯愛好家のグループ内にて問うてみたが、納得のゆく回答を得ることはできなかった。
そんな折、とある海外のサイトで見つけた1枚の絨毯が突破口となり、状況が急展開したのは前述したとおりである。以後は糸で引かれるが如く順調に進んだ。
あたかも、それが必然であるかのように。>/p>
大阪にある国立民族学博物館の収蔵品は、敬三氏のコレクションが母体になっている。
同博物館は、わが国でアンティークのペルシャ絨毯を所蔵する数少ない博物館の1つである。
また、栄一翁は国際交流にも心血を注がれたと聞く。
このたびの考察と調達では満足できる成果を得られたが、これは欧米の絨毯研究家や絨毯商の協力によるところが大きい。
彼らと海を越えて親交を結ぶことができたのもまた、大きな成果である。
身は滅んでも魂は残るという。こうした成果のすべては、敬三氏や栄一翁の導きによって得られたものなのかもしれない。
2022年11月21日
フルーリア株式会社代表取締役 佐藤直行
出典一覧
書籍・雑誌:
- Ford, P. R. J. (1989) . The Oriental Carpet . New York: Portland House .
- 宮内順治 (1930) .「窓掛と敷物」『建築學會パンフレット』3巻 , 9号 , 23頁 .
- 森谷延雄 (1920) .「絨毯の話」『木工と裝飾』、12号 .
ウェブ:
- 清水建設株式会社 (2019) .「140年の時を超えて受け継がれる『旧渋沢邸』」. 清水建設 . https://www.shimz.co.jp/topics/construction/item17/,(参照 2022-10-20)
- OVERSIZED ANTIQUE PERSIAN BAKHTIARI FLORAL HANDWOVEN WOOL RUG BB7119 14’0″ × 22’10” $130,000, Antique Rugs by Doris Leslie Blau, https://www.dorisleslieblau.com/antique-rugs-carpets-persian-bakhtiari-rug-23×14-bb7119/, (参照 2022-11-07)
- AUTHENTIC PERSIAN MALAYER BOTANIC HANDMADE WOOL RUG BB2791 12’3″ × 21’10” $98,000, Antique Rugs by Doris Leslie Blau,
https://www.dorisleslieblau.com/antique-rugs-carpets-persian-malayer-2791-rug/, (参照 2022-11-07)
- Dorokhsh / 21593, WOVEN, https://mobile.woven.is/21593.htm, (参照 2022-11-07)
- Dorokhsh Rug, Rooms To Go, https://blog.roomstogo.com/oriental/persian/dorokhsh/, (参照 2022-10-20)
- Persian Khorasan Dorokhsh Rug, Essie Carpets,
https://www.essiecarpets.com/product/boteh-khorosan-doroksh/, (参照 2022-10-20)
- Antique Persian Dorokhsh Rug – 18’5 × 11’81, RUGS OF LONDON,
https://www.rugsoflondon.com/antique/3676-persian-dorokhsh-rug-8055351.html, (参照 2022-10-20)
- ウィキメディア財団 (2022) .「骨董品」. ウィキペディア .
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/骨董品, (参照 2022-10-20)
- ウィキメディア財団 (2022) .「渋沢敬三」. ウィキペディア .
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/渋沢敬三, (参照 2022-10-20)
- ウィキメディア財団 (2022) .「渋沢栄一」. ウィキペディア . https://ja.m.wikipedia.org/wiki/渋沢栄一, (参照 2022-10-20)