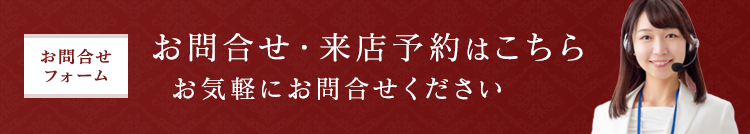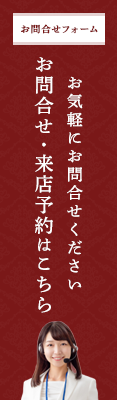フランシスコ教皇の棺の下にペルシャ絨毯が敷かれた理由

[画像:フランシスコ教皇の棺の下に敷かれたヘリズ産ペルシャ絨毯]
2025年4月26日、サン・ピエトロ大聖堂で、フランシスコ教皇の簡素な木製の棺は花畑に囲まれていました。
深紅、藍、オレンジの色合いで織り込まれた複雑な模様は、イタリアの芸術的伝統には属しません。
この精巧な絨毯は、教皇の葬儀に使われた3枚の絨毯のうちの2枚目であり、イラン北西部から来たものです。
フランシスコ教皇の私設礼拝堂、そしてサン・ピエトロ大聖堂、そして4月26日にサン・ピエトロ広場で行われる葬儀で、教皇の棺の下にペルシャ絨毯が敷かれることで、カトリック教会は600年以上続く伝統を踏襲しています。
イタリアの伝統でもキリスト教の伝統でもないペルシャ絨毯が、なぜカトリックの最も神聖な儀式における聖地を表すようになったのか、と疑問に思う方もいるでしょう。
14世紀後半以降、アナトリア(後にレヴァント、エジプト、イラン)から輸入された絨毯は、金で買える最も高価な床敷物でした。
その特別な地位は、宗教画に描かれた絨毯によって証明されており、聖母マリアや他の聖人の足元に絨毯が描かれることがよくあります。
最初期の例の一つは、ニッコロ・ディ・ブオナコルソによる「聖母マリアの結婚」です。
この作品は1380年頃にシエナで制作され、ロンドン・ナショナル・ギャラリーで開催された「シエナ:絵画の興隆」展にも出品されました。
この作品では、対峙する動物たちの意匠をあしらった印象的な絨毯が、マリアとヨセフの結婚式が行われる高貴な空間を区切っています。
現在メトロポリタン美術館に所蔵されているこれに酷似した絨毯は、1990年代に発見されました。
イルハン朝の西方の地域で製作されたものと考えられています。
アンドレア・デル・ヴェロッキオは、1486年に完成した「洗礼者ヨハネと司教ドナート・デ・メディチに挟まれた聖母子像」(通称「マドンナ広場」)にも、アナトリア絨毯を登場させました。
オスマン帝国時代のデザインで、多くの作品が現存するこの絨毯は、聖母子像が安らかに眠る特別な空間を創出しています。
他の二人の人物像が聖母子像に比較的近いことは、絨毯内の配置が示唆します。
聖ヨハネは絨毯の縁に足全体を踏み込んでいますが、ドナート・デ・メディチは片方のつま先だけでその空間に踏み込んでいるのです。
16世紀には、イスラム諸国からヨーロッパへ送られる絨毯の数は増加し、貿易品、直接の注文、そして最高級品は外交上の贈り物として届けられました。
16世紀にはオスマン帝国の絨毯が貿易を支配していました。
17世紀には、サファヴィー朝イラン、そして後にムガル帝国インドが市場に加わりましたが、外交上の贈り物としての絨毯の使用は今日まで続いています。
2016年、イランのハサン・ロウハニ大統領はバチカンでフランシスコ教皇と会談した際、教皇への贈り物としてクム産の小さな絨毯を持参しました。
フランシスコ教皇の葬儀で見られた3枚の絨毯は、絵画に描かれた絨毯とほぼ同じ機能を持っています。
これらは聖地、つまり教皇と周囲の随員や来賓を隔てる明確な境界線を持つ神聖な空間を示すものです。
より親密な雰囲気のプライベートな礼拝堂では、2人のスイス衛兵が絨毯の縁の上で棺の両側に立ち、ヴェロッキオの「マドンナ広場」における洗礼者ヨハネのしぐさを彷彿とさせました。
サン・ピエトロ大聖堂では、一般公開される際に、より大きな絨毯の縁とそれが囲む聖域が支柱で補強されました。
これもイラン北西部産のヘリズ絨毯で、過去2回の教皇葬儀でも使用されたものと思われます。
2005年にはヨハネ・パウロ2世、2023年には名誉教皇ベネディクト16世が葬儀に参列します。
フランシスコ教皇が2024年後半に施行した変更は、サン・ピエトロ大聖堂で前任者たちが用いた高架式の棺台や、糸杉、鉛、オーク材の3種類の棺といった、これまでの教皇葬儀に見られたような華やかさや厳粛さを大幅に排除するものです。
こうした点を踏まえると、絨毯の導入は特別な意味を持ちます。
フランシスコが絨毯の低い位置に置かれた簡素な木製の棺に横たわることで、聖地のイメージが鮮やかに浮かびあがるのです。