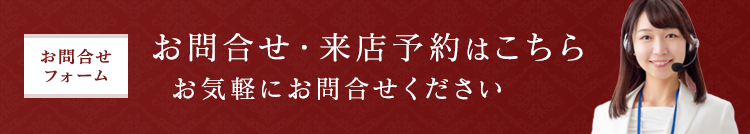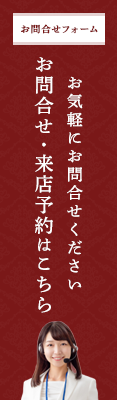中世においてペルシャ絨毯はどのように広まったのか

[画像:マルコ・ポーロ]
中世におけるペルシャ絨毯の広まりは、いくつかの重要な要因によったものと考えられます。
この時期、絨毯の製造技術やデザインはさらに洗練され、商業活動や文化交流が盛んになる中で多くの地域へと広がっていったようです。
「考えられます」「ようです」と歯切れが悪くならざるを得ないのには理由があります。
サファヴィ朝に至るまでの時代に製作されたペルシャ絨毯は一枚も現存しておらず、推測に頼らざるを得ないのが現状だからです。
ルネサンス期のヨーロッパ絵画に登場する絨毯はトルコ製とされており、ホルバイン絨毯、ロットー絨毯などと、それを描いた画家たちの名が付けられています。
また、有名なマルコ・ポーロの『東方見聞録』にもトルコ絨毯についての記述はあっても、ペルシャ絨毯に関する具体的な記述はありません。
とはいえマルコ・ポーロも辿った当時の交易路が、ペルシャ絨毯の広がりに貢献したことは、ほぼ間違いないでしょう。
イランはアジアとヨーロッパを結ぶ交易路として知られるシルクロード上に位置していました。
シルクロードを通じてペルシャ絨毯は東西に運ばれ、そして文化の影響を受けることになったとされます。
商人たちはペルシャ絨毯を商品の一部として積極的に取り扱い、結果としてその美しさを広めることに貢献したものと思われます。
もう一つが十字軍です。
十字軍とは、中世のヨーロッパにおいてキリスト教徒が聖地エルサレムを奪還するために行った軍事遠征のことを指します。
主に11世紀から13世紀にかけて行われ、ローマ教皇の呼びかけに応じて多くの騎士や民兵が参加しました。
十字軍の遠征は8回(7回とする説や9回とする説もあり)にわたって実施されましたが、宗教的な動機に加え、経済的な利益や地政学的な要因も絡んでいました。
最初の十字軍は1096年に始まり、エルサレムを奪還することに成功したものの、その後の遠征は必ずしも成功した訳ではありません。
しかし、十字軍の遠征により東洋の文化や特産品がヨーロッパに伝わることになり、これに促進された東西の流通は、やがてルネサンスの時代の到来に至る契機ともなります。
地中海貿易の担い手であったベネチアとジェノバは十字軍の兵站に関わることで隆盛し、とりわけ第4回十字軍を利用してコンスタンティノープル(のちのイスタンブール)を抑えたベネチアは、この頃、最盛期を迎えています。
十字軍の戦利品としてヨーロッパに持ち込まれたオリエントの絨毯が、ヨーロッパにおける絨毯文化を促進したのは確かでしょう。
とりわけアナトリア(現在のトルコ)で製作された絨毯が持ち込まれ、その芸術性や技術が広まったといいます。
それではペルシャ絨毯はどうだったかと言えば、十字軍とペルシャ絨毯の間には直接的な関係はあまりないとされます。
確かに十字軍の進軍ルート上にイランはありません。
しかし、この時代、トルコとイランはともにセルジュク朝の下にありました。
セルジュク朝は、11世紀から13世紀にかけて中東と中央アジアに存在したテュルク(トルコ)系のイスラム王朝です。
セルジュク朝は初めにイランを征服し、その後大セルジュク朝の名の下でその影響を拡大しました。
とりわけ1071年のマンジケルトの戦いでビザンツ帝国に勝利し、アナトリアへの進出を促します。
セルジュク朝は文化的にも重要で、ペルシャ語やイスラム文化の発展に寄与しましたが、内部の対立や外部からの攻撃(特に十字軍)により衰退し、最終的にはモンゴルの侵攻によって滅亡しました。
セルジュク朝は出自においてはテュルク系ではあるものの、行政ではニザームルムルクを始めとするイラン系の官僚が活躍し、宮廷の公用語はペルシャ語でした。
宮廷にはペルシャ語で詩作する文人が数多く集まりますが、マリク・シャーに仕えたオマル・ハイヤームは四行詩集『ルバイヤート』などで特に有名です。
また、12世紀にアゼルバイジャンのギャンジャで活動したニザーミーは『ホスローとシーリーン』『ライラとマジュヌーン』など、ペルシャ語ロマンス叙事詩の長編作品を残しました。
このようにセルジュク朝の文化・芸術の中心となったのは、イラン人だったのです。
中世に十字軍が遠征した際、彼らが持ち帰った戦利品や交流を通じて、中東地域の文化や技術がヨーロッパに広まりました。
この時、持ち込まれたのはペルシャ絨毯そのものではなく、アナトリア(現在のトルコ)で織られた絨毯であったといいます。
しかし、前述したようにセルジュク朝の文化・芸術の中心となったのがイラン人であったことを考えれば、これらの絨毯がイランの町で製作された可能性も十分に考えられるでしょう。
そもそも、この時代の絨毯については不明な点が多く、産地についても推測に基づいたものであることを知っておく必要があります。
それはさておき、十字軍によって持ち込まれた絨毯はヨーロッパのコレクターや芸術家の間で価値を認められ、ヨーロッパ中に広まりました。
また中東地域で発達した絨毯の織りの技術も、東方への知識とともにヨーロッパに伝わったとされます。
やがて絨毯は美しい室内装飾品としての範疇を脱し、地位や富の象徴として家や宮殿を飾ることになりました。
このため、絨毯は贈答品としても重宝され、ときに外交用とされることもあったようです。
これがオリエントの絨毯が異国の地に広まる契機となりました。
このように中世におけるペルシャ絨毯の広まりは、様々な要因が相まって実現したものでした。
これにより、ペルシャ絨毯は単なる地域特有の製品から、世界中で愛される工芸品へと成長し、その技術や文化は現在に至るまで受け継がれています。
ペルシャ絨毯の歴史を知ることで、その美がどのように形成されてきたのかのみならず、真の価値や人を惹きつけてやまない訳を理解することができる筈です。